質の高い睡眠とは?睡眠の質を向上させる7つの方法を解説!
2025.08.14

「朝起きても体がだるい」「夜中に何度も目が覚めてしまう」などの悩みを抱えている方は少なくないでしょう。
近年の国民健康・栄養調査によると、睡眠で休養がとれていると感じている方の割合は8割程度です。2割近くの方は睡眠で十分な休息が得られていないと感じている現状があります。
起床時に心身が十分に回復したと感じられる、質の高い睡眠を取るためには、いくつかのポイントがあります。
本記事では、睡眠の質をチェックする方法や、睡眠の質を向上させる7つの方法について解説します。
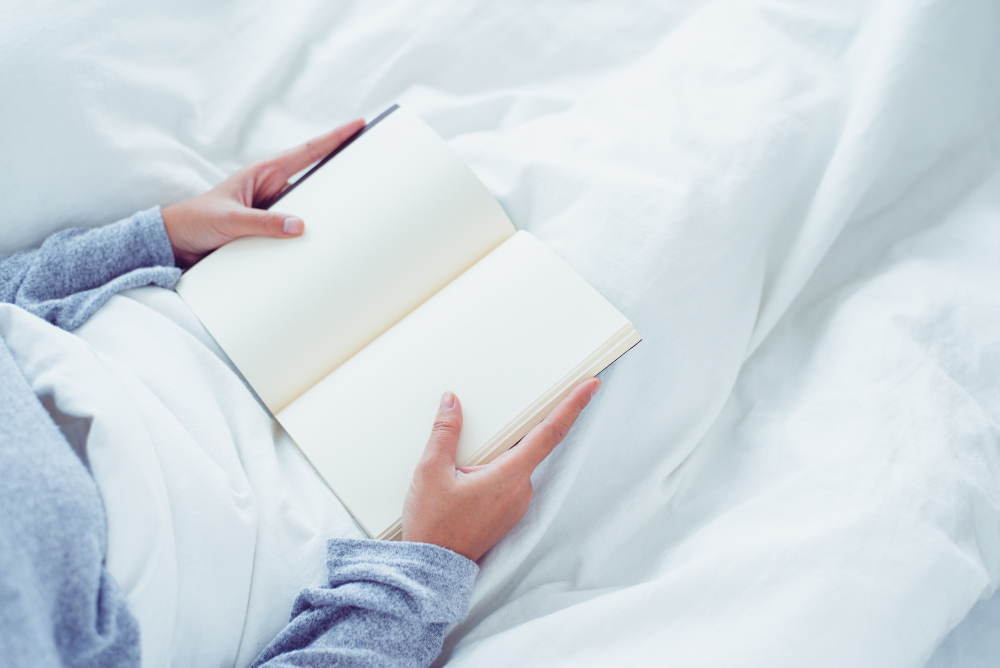
質の高い睡眠とは?睡眠の質をチェックしてみよう!
まずは質の高い睡眠の特徴を知り、睡眠の質をチェックしてみましょう。
質の高い睡眠とは、睡眠時間の長さだけではなく、起床時にリフレッシュしたと感じられる睡眠を指します。
質の高い睡眠の特徴として、以下のポイントが挙げられます。
入眠までの時間が約30分以内と短い
中途覚醒が少ない
早朝に目が覚めても再入眠できる
起床時に熟眠感や爽快感がある
日中の強い眠気がない
朝起きたときの気分や日中の様子を振り返り、該当する項目が多ければ、質の高い睡眠が取れている可能性が高いです。一方、朝起きても疲れが取れなかったり、夜中に何度も目が覚めてしまったりする方は、睡眠の見直しが必要かもしれません。
睡眠日誌をつけると、より正確に睡眠の質を評価できます。手帳やスマートフォンのアプリなどを活用してみるのもおすすめです。

睡眠の質を向上させる3つのメリット
1.集中力・パフォーマンスを向上させる
よく眠れず、ぼんやりとした状態で受けたテストで、思うような成果が出せなかった経験のある方は少なくないでしょう。
私たちが経験的に知っているように、質の高い睡眠を取るメリットの一つは、日中の集中力・パフォーマンス・創造性が向上することです。一方で睡眠不足や睡眠の質が低下すると、仕事の正確性や生産性が下がります。
重要な会議やプレゼンテーション、試験の前日は、特に睡眠の質を意識してみましょう。
2.メンタルを安定させる
感情のコントロールを助け、メンタルを安定させることも、質の高い睡眠を取るメリットの一つです。
満足な睡眠が取れていない状態が続くと、ストレスホルモンが過剰に分泌され、自律神経の乱れを引き起こします。自律神経の乱れにより生じる精神症状は、不安や抑うつなどです。
また睡眠不足により、脳内で感情処理を担う扁桃体が、ネガティブな刺激に反応しやすくなることがわかっています。
日本の成人を対象とした研究では、睡眠による休養感が低い人ほど、抑うつの度合いが高いことが明らかになっています。ストレスや不安を感じやすい方は、睡眠の質や量を見直すことでメンタルが安定するかもしれません。
3.心血管疾患や高血圧の発症率を低下させる
質の高い睡眠は、高血圧や心疾患などの発症リスクを下げるといわれています。
睡眠中は日中と比較して血圧や心拍数が低下し、心血管系にとって休息となる時間です。睡眠不足により、心臓や血管に負担がかかります。
睡眠により休息が取れたと感じている方ほど、心筋梗塞・狭心症・心不全などの心血管疾患の発症率が低く、若年成人と女性ではこの関連が顕著であることが明らかになっています。

睡眠の質を向上させる7つの方法
1.寝る前の習慣を整える
寝る前の過ごし方は、スムーズな入眠と質の高い睡眠に大きく影響します。心身をリラックスさせ、睡眠モードへと導く習慣を作りましょう。
睡眠の質を向上させるために取り入れるべき習慣は、以下の3つです。
寝る2時間前からデジタルデバイスの使用を控える:ブルーライトは脳を覚醒させ、入眠を妨げる。
就寝1〜2時間前にお風呂(38〜40℃)に30分程度浸かる:手足の血管が広がり、体の熱が放散されて体温が下がることで、眠気を誘う。
自分に合ったリラックス方法を取り入れる:ストレッチ・瞑想・アロマ・音楽などを寝る1時間前に取り入れることで、副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる。
これらの習慣を毎日続けることで、入眠までの時間が短くなり、質の高い睡眠が得られます。
2.寝室の環境を見直す
寝室環境を整えることも、スムーズな入眠と深い眠りを促すために重要です。快適な寝室環境づくりのポイントを4つ紹介します。
体に合った枕やマットレスを選ぶ:体圧が分散され、無理のない姿勢で眠れる寝具は、体の負担を軽減する。
できるだけ暗くする:光を浴びると、睡眠を促すメラトニンの分泌が抑制され、眠りの妨げとなる。寝室にデジタル機器を持ち込まず、遮光カーテンを活用するなどの工夫をする。
静かな環境をつくる:騒音も睡眠効率の低下や中途覚醒につながる。防音材や二重窓を導入する、耳栓を活用するなどの対策をとる。
温度・湿度を調整する:寝室の理想的な室温は20℃前後、湿度は50%前後とされている。季節に応じてエアコンや加湿器、除湿器などを活用する。
寝室は一日の疲れを癒す大切な場所です。上記のポイントを見直すことで、睡眠の質が上がる可能性があります。自分に合った心地よい環境を探してみましょう。

3.生活リズムを整える
安定した睡眠リズムを作るには、規則正しい生活リズムが欠かせません。特に重要なのが、起床時に光を浴びることと、決まった時間に起きることです。
朝の光を浴びる: 朝に太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされる。睡眠を促すホルモンの分泌が抑制されて活動モードに切り替わり、夜には自然な眠気が訪れる。
起床時間を決める:起床時間が不規則だと、体内時計の乱れにつながる。起床時間が遅れると、夜の寝つきが悪くなり、十分な睡眠時間が確保できない。
上記の理由から、起きたらカーテンを開けて日光を浴びたり、散歩に出かけたりすることをおすすめします。また、毎日できるだけ同じ時間に起きることを意識し、体内時計を安定させることが重要です。
4.運動習慣を作る
適度な運動は、睡眠の質を向上させるために効果的です。定期的な運動により、以下の効果が期待できます。
入眠促進:体に適度な疲労が加わり、寝つきが良くなる。
中途覚醒の減少: 夜間目が覚める回数が減る。
睡眠休養感の向上: 熟眠感が得られ、目覚めた時の爽快感が高まる。
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動だけでなく、筋力トレーニングも睡眠改善に効果があるとされています。
厚生労働省は健康増進の観点から、1日60分程度の運動を推奨しています。しかし、まとまった時間が確保できなくても諦めず、少しずつでも定期的に運動を取り入れることが重要です。
ただし、就寝直前の激しい運動は体を興奮させてしまい、かえって眠りを妨げる可能性があるので注意しましょう。運動は就寝の2〜4時間前までに済ませるのが理想的です。
5.食生活を見直す
食事内容やタイミングは睡眠に影響します。体内時計を整え、快適な睡眠を得るために見直すべきポイントは以下の4つです。
朝食を規則正しく摂る:朝食は体内時計の調整に関連する。朝食を食べないことで体内時計が後退し、寝つきが悪くなる。
夜食や間食を控える:就寝前の夜食や間食は体内時計を後退させ、睡眠の質を低下させる。
減塩を心がける:食塩の過剰摂取により、水分摂取量が増え、夜間の排尿回数が増えると睡眠に悪影響を与える。
バランスの良い食事を心がける:主食・主菜・副菜を中心に様々な食品を取り入れ、栄養バランスを意識した食事を摂る。
規則正しい食事リズムや栄養バランスを心がけることで、体内時計が整い、質の高い睡眠へとつながります。

6.カフェイン・アルコール摂取習慣を見直す
カフェイン・アルコールは、睡眠の質に大きく影響する嗜好品です。適切な摂取量とタイミングを知り、摂取習慣を見直すことも睡眠の質を向上させます。
1日のカフェイン摂取量を400mgまでにする:カフェインには覚醒作用があり、寝つきの悪化や睡眠の質を低下させる。ドリップコーヒー4杯分(700cc)、ペットボトルコーヒー1.5本分(750cc)程度を目安にする。
夕方以降はカフェインを控える:夕方以降の摂取は夜間の睡眠に影響する。麦茶やハーブティーなど、カフェインを含まない飲料に置き換える。
アルコール摂取量を控える:アルコールは一時的に寝つきを促進するが、睡眠後半の質を悪化させ、中途覚醒につながる。
カフェインとアルコールの適切な摂取量とタイミングを意識することで、睡眠の質の改善が期待できます。
7.ストレス管理を見直す
ストレスは睡眠の質に大きく影響します。日中のストレスが原因で寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めたりすることは少なくありません。ストレスを適切に管理することで、心身ともにリラックスでき、質の高い睡眠へとつながるでしょう。
具体的には、以下の方法が挙げられます。
趣味に没頭する時間を作る:気分転換になり、ストレス解消につながる。
瞑想時間を確保する:脳への刺激を減らし、リラックスしやすくなる。
悩みを書き出す:紙に書き出すことで頭の中が整理され、気持ちが楽になる。

まとめ:睡眠の質を向上させて、もっと快適な毎日へ
睡眠は私たちの生活の質を左右する重要な要素です。意識的に睡眠の質改善に向けた行動を取ることで、より充実した生活を送れます。
本記事でご紹介した7つの方法を実践すれば、あなたの睡眠の質は少しずつ向上するはずです。
まずはひとつだけでも習慣を見直し、継続することが質の良い睡眠につながります。質の高い睡眠を手に入れて、さらに快適でエネルギッシュな毎日を送りましょう。
【参考文献】
厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド 2023 p.11〜14・22〜31
Jnet21 仕事のパフォーマンスと睡眠の関係性について教えてください。 | ビジネスQ&A
しっかり眠って心身をメンテナンス ストレスに負けない体をつくる睡眠
睡眠不足で情動不安定や抑うつに | Science Portal
厚生労働省 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023 p.7
RANKING
-
 常に挑戦できる自分になりたい人必見!「セルフ・エフィカシー(自己効力感)」を高めよう-前編-
常に挑戦できる自分になりたい人必見!「セルフ・エフィカシー(自己効力感)」を高めよう-前編- -
 ファスティング(断食)のメリット・デメリットとは?初心者におすすめの方法や注意点まで徹底解説!
ファスティング(断食)のメリット・デメリットとは?初心者におすすめの方法や注意点まで徹底解説! -
 自分を責めすぎる方必見!自分に優しくする「セルフ・コンパッション」で心を軽くしよう
自分を責めすぎる方必見!自分に優しくする「セルフ・コンパッション」で心を軽くしよう -
 アンガーマネジメントとは?怒りをコントロールして職場・家庭の人間関係を豊かにする実践法
アンガーマネジメントとは?怒りをコントロールして職場・家庭の人間関係を豊かにする実践法 -
 仕事のパフォーマンスを向上させるには?心と体を整える「上手な休み方」を徹底解説!
仕事のパフォーマンスを向上させるには?心と体を整える「上手な休み方」を徹底解説! -
 質の高い睡眠とは?睡眠の質を向上させる7つの方法を解説!
質の高い睡眠とは?睡眠の質を向上させる7つの方法を解説! -
 デジタルデトックスとは?日常生活に取り入れる3つのメリットと具体的な方法を解説!
デジタルデトックスとは?日常生活に取り入れる3つのメリットと具体的な方法を解説! -
 WELL Being -社会-編 3 無理に付き合わないコミュニケーション術:本当に大切な人との関係を深める方法
WELL Being -社会-編 3 無理に付き合わないコミュニケーション術:本当に大切な人との関係を深める方法 -
 WELL Being -社会-編 2 孤独を力に変える:一人の時間を活かすウェルビーイング術
WELL Being -社会-編 2 孤独を力に変える:一人の時間を活かすウェルビーイング術 -
 WELL Being -社会-編 1 “つながり”の力:人間関係が私たちの寿命を左右する理由
WELL Being -社会-編 1 “つながり”の力:人間関係が私たちの寿命を左右する理由
